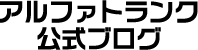ウイスキー保管のコツ! 自宅からトランクルームまで完全ガイド
香り高く味わいも深いウイスキーは、グラスに注いでゆっくりと琥珀(こはく)色の輝きを楽しむのがぴったりの「大人のお酒」です。ウイスキーにはさまざまな種類があり、リーズナブルなものから高価なものまで幅広くそろっています。
そんなウイスキーを愛飲する人にとって共通のお悩みといえば「どうやって保存するのが一番いいのか」ということでしょう。高価なウイスキーは時間をかけてじっくり楽しみたいものですが、保存方法が悪いとせっかくの香りや味が損なわれてしまいます。
そこで、ここではウイスキーの保存に関してのお役立ち情報をご紹介しましょう。
この記事は次のような方におすすめです
- ウイスキーの正しい保存方法を知りたい方
- 開封後のウイスキーの品質をできるだけ長く保ちたい方
- ウイスキーを保管してはいけない場所を知りたい方
- 増えてきたウイスキーの保管場所として外部サービスを検討している方
1. ウイスキーの基本的な保存知識
お酒は、種類によって冷蔵庫で冷やす、冷暗所に置くなどして保存するのが一般的です。では、ウイスキーはどのように保存すればいいのでしょうか。ここでは、賞味期限や正しい保存方法、気を付けるポイントなどをご紹介します。
1-1. ウイスキーの賞味期限と品質保持
そもそも、ウイスキーには賞味期限はあるのでしょうか。ウイスキーはアルコール度数が高い(約40~60度)ため「品質が安定しているお酒」といわれています。そのために、正しい保存状態で未開封であれば、長い間品質を保つことが可能です。
ボトルに詰めてから30年以上経過している「オールドボトル」(長期間保存された希少なウイスキー)が根強い人気を保っているのも、ウイスキーの寿命の長さを物語っています。年月がたっても体に支障をきたすような変質はしにくいために、法律でも賞味期限の記載は義務付けられていないのです。
1-2. 開封後の保存場所は?
開封後のウイスキーを保存するときは、まず、キャップをしっかりと閉めてください。そして、直射日光が当たる窓際や家具の上などに置くのは避けましょう。湿気や強い匂いを放つ場所も避け、冷暗所に「立てて」保存してください。冷蔵庫は、ほかの食品の匂いが移ったり、冷え過ぎて香味成分が凝固し白濁したりする可能性があるため、おすすめはできません。
1-3. ウイスキーの保存で気を付けるポイント
ウイスキーはきちんと保存すれば、未開封でも開封後でもおいしく味わうことができます。そのためには、保存環境に十分気を付けたいものです。特に「温度」「湿度」「紫外線」、そして開封後は「空気」に触れないようにするなど気を配りましょう。それぞれの詳細は、後の項でご紹介します。
1-4. ウイスキー保存のコツ
ウイスキーは、未開封であれば長期間品質が変わらないお酒です。しかし、1度開封したら保存は未開封のときよりも気を付けなければいけません。高価なウイスキーの場合は、少しずつ飲んでゆっくりと楽しみたいものですが、開封後の味や香りの変化は保存状態や個々のウイスキーによって異なります。
一般的に、開封後も数ヶ月は大きな変化はありませんが、ボトルの残量が減る(=瓶内の空気の割合が増える)と、徐々に酸化が進み、香りや味わいが変化(劣化)しやすくなります。香りや味わいが衰えないうちに飲み切るのが理想的です。
2. ウイスキーの正しい保存法
ウイスキーを楽しむためには保存方法に気を付けることが大切です。ここでは、具体的な方法をご紹介します。
2-1. ウイスキー保存に理想的な環境は?
ウイスキーは、アルコール度が高く品質は安定しているとはいえども、デリケートな部分もあります。保存するときの「理想の環境」とは、どのようなものなのでしょうか。
2-1-1. 温度
ウイスキーの保存は、温度の高い場所や温度変化が激しい場所は禁物です。特に以下の場所は避けてください。
| 避けるべき場所 | 理由 |
|---|---|
| 直射日光が当たる窓際や家具の上 | 温度上昇と紫外線(劣化原因)のため |
| 日当たりのいい室内 | 温度上昇と紫外線のため |
| ガスコンロや暖房器具のそば | 高温になるため |
| エアコンの風が直接当たる場所 | 急激な温度変化や乾燥のため |
| テレビやパソコンなど熱を持つ家電のそば | 温度上昇のため |
家の中で一番暗く涼しく、温度が一定している場所(一般的に15~20℃程度が理想)を探しましょう。クローゼットや押し入れ、食器棚やサイドボードの中などが向いています。ただし、「1-2」で触れたように、冷蔵庫での保存はおすすめできません。
2-1-2. 湿度
ウイスキーの味わいにとって湿度は重要ですが、それは樽で熟成させる段階の話です。ボトル詰めされたウイスキーを保管する場合、特に未開封のものは、高すぎる湿度は避けるべきです。ラベルにカビが生えたり、コルク栓の場合はコルクが劣化したりする原因になります。(理想は湿度70%前後と言われますが、家庭での厳密な管理は困難です)
2-1-3. 紫外線
基本的に、ウイスキーに限らず酒類を日差しが当たる場所で保存するのは厳禁です。温度が上がるのはもちろんですが、紫外線もウイスキーが劣化する原因になります。紫外線は、分厚く濃い色のボトルでも貫通して中身に悪影響を及ぼすのです。直射日光はもちろんのこと、太陽の日差しだけで十分に明るい室内に置くのもやめましょう。
ウイスキーが入っている外箱は、強度だけではなく光をさえぎる効果もあります。開封前も開封後も外箱に入れたまま保存するほうが賢明です。
2-1-4. 匂い
「暗くて涼しい場所」として冷蔵庫やクローゼットを選ぶ方もいますが、匂いには注意が必要です。ウイスキーは(特に開封後は)周囲の匂いを吸着しやすい性質があります。ネギやにんにくなど匂いの強い食品、防虫剤や芳香剤などがある場所は避けましょう。
2-2. ウイスキーのおすすめ保存・保管方法
ウイスキーをより良い状態で保管するために、試していただきたい方法をご紹介します。
2-2-1. 箱に入れて保管
ウイスキーは基本的に外箱付きで販売されています。厚手の紙製から重厚な雰囲気の木箱までさまざまです。もともと、ウイスキーの外箱や化粧箱は、光(紫外線)を遮断するように作られています。購入後すぐに箱を捨ててしまう人もいますが、ウイスキーの品質を保つためには外箱に入れたまま保存するのが一番です。衝撃から守ってくれるメリットもあります。ワインとは異なり、コルク栓のものでも立てて保管するのが一般的です(ウイスキーの高いアルコール度数がコルクに触れ続けるとコルクが劣化するため)。
2-2-2. アルミシートやアルミホイル
ウイスキーを外箱に保存するときに、より完璧な紫外線対策を施すなら市販のアルミシートやアルミホイルを使用するのもおすすめです。ボトル全体にぐるぐると巻き付けるか、箱の内側にカットしたものを貼り付けてください。
2-2-3. パラフィルム(開封後)
ウイスキーを開封した後は、きっちりとフタをすることが大切です。けれども、どうしてもボトルとキャップの間にわずかなすき間はできてしまいます。この部分からアルコールが蒸発したり、外の空気が侵入したりすることを防ぐのが「パラフィルム」です。
パラフィルムは、主に実験室などで容器を長期間保存する際に使われる、伸縮性のあるフィルムです。ボトルキャップとボトルのつなぎ目に引っ張るようにして密着させて巻き付けることで、ウイスキーの香りや味が飛ぶのを防ぐ効果が期待できます。
2-2-4. オールドボトルの注意点
「オールドボトル」とは、少なくとも10年以上経過し、現在は販売終了になっているような古いウイスキーを指します。ウイスキー愛好家に人気がありますが、当時のキャップ(特にコルク)の気密性は現在ほど高くない場合があります。高温の場所に置くと未開栓でも中身が蒸発する可能性があるため、パラフィルムで栓の部分を密閉するなどの対策を施し、冷暗所で慎重に保存することが大切です。
2-3. ウイスキーをしまう前に気を付けること
自宅でウイスキーを飲むときには、後片付けも重要です。暖房が効いている部屋で栓を開けたまま朝まで放置すると、味も香りも劣化してしまいます。面倒でも、きちんと栓を閉め(必要ならパラフィルムを巻き)、箱の中に入れ、元の冷暗所に戻してください。
2-4. ウイスキー保存時に気を付けること(地震対策)
「2-1」でご紹介した環境面に加え、もうひとつ忘れてはいけないのが地震対策です。バーのように棚の上にボトルを並べると見栄えは良いですが、震度の強い地震の場合、床に落ちて割れてしまう危険性が高くなります。ガラスボトルが割れると、お酒がだめになるだけではなく、後片付けも大変です。高価なお酒ほど飾りたくなりますが、ウイスキーは箱に入れたまま、できるだけ「低い場所」に保存するようにしてください。
3. ウイスキー保管でトランクルームを検討する際の注意点
自宅に十分な保管スペースがない、または理想的な環境を維持するのが難しい場合、トランクルームの利用を検討する方もいるかもしれません。しかし、ウイスキーのようなデリケートな酒類を預ける場合は、契約前に必ず確認すべき重要な注意点があります。
3-1. 保管が可能か、まず規約を確認する
最も重要な点です。トランクルームの事業者によっては、利用規約で「酒類」や「液体物」の保管を一切禁止している場合があります。
「アルコール類は発火の危険性がある」「万が一ボトルが割れて中身が漏れ出し、他の利用者の荷物に損害を与えた場合のリスクがある」といった理由からです。まずは検討しているトランクルームの規約を熟読し、不明な点は必ず事業者に問い合わせて、ウイスキーの保管が可能かどうかを真っ先に確認してください。
3-2. ウイスキー保管に必要な環境・設備か確認する
保管が許可されている場合でも、保管環境がウイスキーに適しているとは限りません。特に以下の点を確認する必要があります。
- 温度・湿度管理の有無とレベル: 屋外のコンテナ型トランクルームは、外気温の影響を直接受けるため、ウイスキーの保管には絶対に適しません。必ず「屋内型」で「空調設備完備」の施設を選びましょう。ただし、「空調完備」とあっても、それがウイスキーの理想(15~20℃程度、湿度70%前後)を維持するものなのか、単なる換気や冷暖房なのかは事業者によります。具体的な温度・湿度の管理状況(設定温度など)を確認することが重要です。
- セキュリティ: 高価なコレクションを預ける場合、防犯カメラや入退室管理システムなど、セキュリティ対策が十分かも確認しましょう。
3-3. 補償(保険)の範囲を確認する
多くのトランクルームでは、火災や盗難に備えた保険が付帯していますが、その補償内容も確認が必要です。規約で保管が禁止されていなくても、万が一の事故の際に「酒類は補償の対象外」となっているケースもあります。大切なウイスキーコレクションを預ける場合は、補償の対象となるか、対象となる場合の限度額はいくらかを、事前に確認しておきましょう。
4. ウイスキーの保存に関するよくある質問
Q.コルク栓の上等なウイスキーをいただきました。保存で気を付けることはありますか?
A.基本的な保存方法は同じですが、コルク栓は長期間立てておくと乾燥して収縮し、気密性が失われる可能性があります。かといってワインのように寝かせると、高いアルコールがコルクを劣化させてしまいます。立てて保存しつつ、コルクが乾燥しすぎないよう、極端に乾燥した場所は避けるのが賢明です。長期保存の場合はパラフィルムで栓の部分を密閉する対策も有効です。
Q.実家を整理中、押し入れから10年以上前の古いウイスキーが出てきました。飲めますか?
A.ウイスキーはアルコール度数が高い蒸留酒のため、保存状態がよければ(未開封で適切に保管されていれば)品質が安定しており、飲んでも問題ない可能性が高いです。ただし、押し入れが高温多湿であったり、防虫剤やカビの匂いが強かったりした場合、品質が劣化している可能性もあります。開封して透明なグラスに移し、色・香り・沈殿物の有無などを確かめ、少量だけ味見をして判断することをおすすめします。
Q.残り少なくなったウイスキーは、ほかの容器に移し替えてもいいですか?
A.瓶内の空気の割合が多いと酸化が進みやすいため、密閉性の高い小さなガラス瓶などに移し替えるのは有効な方法です。ただし、移し替える際にも空気に触れるため、移し替えた後はできるだけ早めに飲み切ることをおすすめします。
Q.トランクルームの申し込みをしたらすぐに利用できるでしょうか。
A.事業者によってシステムは異なります。多くの場合、Webや電話で申し込み後、審査、契約手続き、初期費用の入金確認が取れ次第、利用可能(鍵の受け取りなど)となります。詳細は各事業者に直接お問い合わせください。
Q.トランクルームに未開封と開封済みのウイスキーを両方置いてもいいですか。
A.まず大前提として、「3-1」で述べた通り、その事業者がウイスキー(酒類)の保管を許可しているかを確認してください。その上で、事業者によっては「開封済みの食品・飲料」の保管を別途禁止しているケースもあります。規約をよく確認し、必ず事業者に問い合わせてください。仮に許可された場合でも、開封後のウイスキーは味や香りの変化が早まるため、ご自宅で早めに楽しむことをおすすめします。
まとめ
ウイスキーはアルコール度数が高いため、長期間品質が安定し、味や香りが変わりにくいのが魅力です。しかし、それは「適切な環境」で保存されてこそ。高温・多湿・紫外線・強い匂いを避け、正しく保存することが、そのウイスキー本来の美味しさを保つ鍵となります。
家の中で最適な保存場所が見つからない場合、選択肢の一つとしてトランクルームが考えられます。ただし、全てのトランクルームがウイスキーの保管に適しているわけでは決してありません。本記事で解説したように、「アルコール類の保管が規約で許可されているか」をまず確認し、さらに「温度・湿度の管理状況はウイスキーに適しているか」「補償の範囲は十分か」など、デリケートなウイスキーの品質を保てる環境かどうかを、ご自身の目でしっかり見極めてから契約することが何よりも重要です。手間を惜しまず、大切なウイスキーを最高の状態で楽しむための場所と方法を見つけてください。